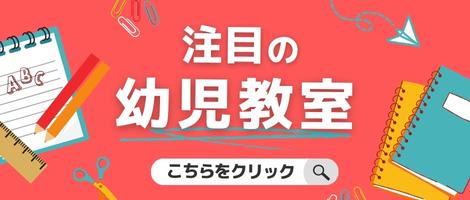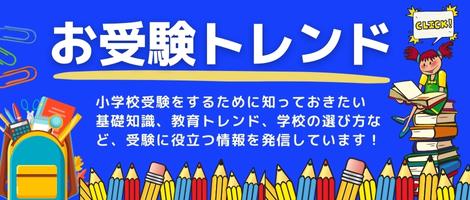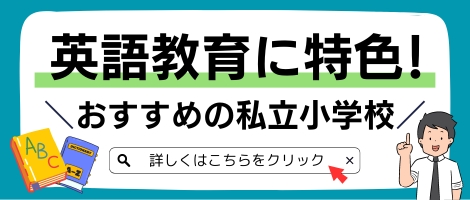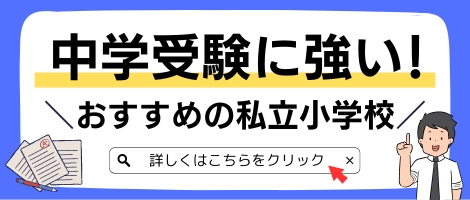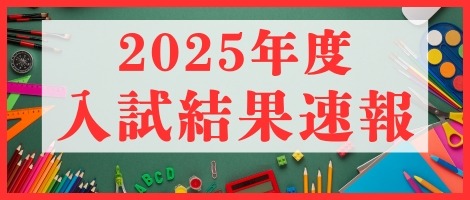森村学園初等部
ICTの活用により「試行錯誤」や「教え合い」を重ねて成長する子どもたち
森村学園初等部では2017年からiPadを導入し、ICTを活用した教育を行っています。同校には、Apple社が教育分野のイノベーターとして認定する「ADE(Apple Distinguished Educator)」に選出された教員が3名在籍しており、それぞれの得意分野を活かしてICTを活用。その1人であり、国内外から授業見学や講演などの依頼を受けている榎本昇先生にお話を聞き、3年生の授業を取材しました。
森村学園初等部 ICT担当 榎本昇先生のお話
• データの分析により見えてきた成果
• プログラミングを通して生まれる「教え合い」
• 入賞常連校に成長した「KWN日本コンテスト」での経験
• 家庭でのルール作りの重要性
• 他国からも注目されるICT教育
• プログラミングの授業(3年生)を取材
森村学園初等部 ICT担当 榎本昇先生のお話
• データの分析により見えてきた成果
• プログラミングを通して生まれる「教え合い」
• 入賞常連校に成長した「KWN日本コンテスト」での経験
• 家庭でのルール作りの重要性
• 他国からも注目されるICT教育
• プログラミングの授業(3年生)を取材

ICT担当 榎本昇先生
森村学園初等部 ICT担当 榎本昇先生のお話
データの分析により見えてきた成果
本校では2017年にiPadを導入しましたが、当時と比べるとデバイスも進化していますし、情報のやりとりも1対1から複数での共有へと変化しています。1つの制作物をみんなで共有しながら作っていくのが今では普通になっていますが、2017年には想像していなかったことです。通常は子どもたちによる校内放送を音声のみで行っていますが、映像で見せたいことがあると言ってきたときはZoomでライブ配信することもできます。映像制作やMinecraftカップの打ち合わせなども、Zoomで行えるようになりました。技術や状況の変化に対応する意味でも、ICT教育のカリキュラムは毎年変えています。
プログラミングの授業は感覚に頼るのではなく、きちんとデータを取って効果の検証も行っています。4年生以上は授業後に振り返りのコメントを提出してもらっていますが、授業を始めてから4年間で10832のデータが集まりました。それを分析して、どんな授業をしたらどんな力が伸びたかをデータ化しています。例えば、私が手を放せば放すほど、子どもたちの試行錯誤が増えることがわかりました。本気で何かを作ろうと1人で試行錯誤すると創造力の数値も伸びて、自分で考えるとそれを人に話したくなるので自己肯定感も高まるということがデータから見えてきています。
プログラミングの授業は感覚に頼るのではなく、きちんとデータを取って効果の検証も行っています。4年生以上は授業後に振り返りのコメントを提出してもらっていますが、授業を始めてから4年間で10832のデータが集まりました。それを分析して、どんな授業をしたらどんな力が伸びたかをデータ化しています。例えば、私が手を放せば放すほど、子どもたちの試行錯誤が増えることがわかりました。本気で何かを作ろうと1人で試行錯誤すると創造力の数値も伸びて、自分で考えるとそれを人に話したくなるので自己肯定感も高まるということがデータから見えてきています。


プログラミングを通して生まれる「教え合い」
プログラミングに関しては、各学年で取り組む内容はそれほど変わりません。学年に応じて、ノーコード、ローコード、言語を使ったコーディングというように差別化していますが、プログラミングの原則に沿った内容を発達段階に応じて繰り返し行っています。4年生でもアプリを作れますし、5年生や6年生との差は使う手法が違うだけで内容はそれほど変わりません。4年生以上はアプリを作るときに、どんな人に使ってほしいか、性別や年齢、使っている言語などをプロファイリングしてから作り始めます。アート作品と同じように、せっかく作っても、価値がわからない人には価値がないものになってしまいますし、自己満足で終わってしまうからです。考えてから作り始めると、完成度が全然違います。一方で、3年生までは楽しく作ればいいという方針で授業を進めています。
プログラミング教育というと、論理的思考力や将来エンジニアになるためのスキルが身につくなどの点に目を向けることが多いですが、私はそれをメインの目的とはしていません。プログラミング自体が目的ではなく、プログラミングを通じて試行錯誤することが大切だと考えています。大人になったときにどれだけ試行錯誤できるか、どれだけクリエイティブなことができるようになるか、その素地を育んでいきたいのです。失敗や子ども同士の教え合いにこそ価値があると思うので、教員は最低限のことしか教えません。インプットされたものをアウトプットするためには言語化しなければならないので、子ども同士の教え合いは言語化の練習にもなります。
プログラミングの素地にはほとんど差がないので、国語や算数の授業ではあまり発言しない児童が、プログラミングのときは積極的に教え合いに参加している場面も見られます。もし本格的にプログラミングのスキルを学びたいなら、1人の方が効率もいいでしょう。しかし、教え合いなど「みんなで学ぶ」ということに、学校に来る意味があるのです。一度しかない小学校生活の中で、この経験はきっと何かにつながる引き出しになります。プログラミングを通した経験が始点となり、その延長線上にエンジニアへの道があるかもしれませんし、この経験があるからこそつながる道がどの児童にも見えてくると思います。
プログラミング教育というと、論理的思考力や将来エンジニアになるためのスキルが身につくなどの点に目を向けることが多いですが、私はそれをメインの目的とはしていません。プログラミング自体が目的ではなく、プログラミングを通じて試行錯誤することが大切だと考えています。大人になったときにどれだけ試行錯誤できるか、どれだけクリエイティブなことができるようになるか、その素地を育んでいきたいのです。失敗や子ども同士の教え合いにこそ価値があると思うので、教員は最低限のことしか教えません。インプットされたものをアウトプットするためには言語化しなければならないので、子ども同士の教え合いは言語化の練習にもなります。
プログラミングの素地にはほとんど差がないので、国語や算数の授業ではあまり発言しない児童が、プログラミングのときは積極的に教え合いに参加している場面も見られます。もし本格的にプログラミングのスキルを学びたいなら、1人の方が効率もいいでしょう。しかし、教え合いなど「みんなで学ぶ」ということに、学校に来る意味があるのです。一度しかない小学校生活の中で、この経験はきっと何かにつながる引き出しになります。プログラミングを通した経験が始点となり、その延長線上にエンジニアへの道があるかもしれませんし、この経験があるからこそつながる道がどの児童にも見えてくると思います。


入賞常連校に成長した「KWN日本コンテスト」での経験
本校は2010年度から、パナソニックが主催する「KWN(キッド・ウィットネス・ニュース)日本コンテスト」に参加しています。「SDGs」を意識した「今、つたえたいこと」をテーマに、映像作品づくりに取り組むコンテストです。毎年、有志の5年生か6年生が授業時間外に映像を制作しています。今年度は6年生が取り組んでいますが、子どもたちが決めたテーマは「金継ぎ」です。「金継ぎ」は、漆を使って欠けたり割れたりした器を修復する伝統的な技法ですが、関心を持ってずっと温めてきた児童が「金継ぎ」をテーマにしたいと提案しました。壊れたものを修復して利用する技術があることや、買った方が早いのになぜ修復するのかという点に関心を持ったようです。
テーマや取材対象を決めるときも、教員はほとんど口を出しません。取材対象者はインターネットを活用して自分たちで見つけて、基本的にアポ取りをするのも子どもたちです。取材対象を決めた時点で教員が確認しますが、子どもたちでも大丈夫そうな場合は直接アポを取ります。今年度は、職人さんや名古屋の陶磁器メーカー「ノリタケ」などに取材をしました。下調べをして質問を考えるだけでなく、返ってきた答えに応じて重ねて質問する練習もしてから取材に行きます。インタビューの様子などを撮影し、1つのストーリーとして編集して完成させるまで、すべて子どもたちが行っています。
テーマ決めから完成までの経験を通して、スキルとしてはそれほど大きな成長はないかもしれませんが、自信がつくので物怖じしなくなります。映像制作を経験して、現在大学生になった卒業生は、高校生のときにカンボジアの電気事情に興味を持ち、自分でカンボジアの企業などにアポを取ったそうです。大学生のうちに現地へ行って話を聞きたいので、英語の勉強も頑張っていると聞きました。卒業生の声などからも、行動すれば何かが変わるという経験をした児童は、その経験がその後の活動で1歩を踏み出すための引き出しになっているのだと実感できます。
テーマや取材対象を決めるときも、教員はほとんど口を出しません。取材対象者はインターネットを活用して自分たちで見つけて、基本的にアポ取りをするのも子どもたちです。取材対象を決めた時点で教員が確認しますが、子どもたちでも大丈夫そうな場合は直接アポを取ります。今年度は、職人さんや名古屋の陶磁器メーカー「ノリタケ」などに取材をしました。下調べをして質問を考えるだけでなく、返ってきた答えに応じて重ねて質問する練習もしてから取材に行きます。インタビューの様子などを撮影し、1つのストーリーとして編集して完成させるまで、すべて子どもたちが行っています。
テーマ決めから完成までの経験を通して、スキルとしてはそれほど大きな成長はないかもしれませんが、自信がつくので物怖じしなくなります。映像制作を経験して、現在大学生になった卒業生は、高校生のときにカンボジアの電気事情に興味を持ち、自分でカンボジアの企業などにアポを取ったそうです。大学生のうちに現地へ行って話を聞きたいので、英語の勉強も頑張っていると聞きました。卒業生の声などからも、行動すれば何かが変わるという経験をした児童は、その経験がその後の活動で1歩を踏み出すための引き出しになっているのだと実感できます。


家庭でのルール作りの重要性
インターネットの使用について不安を感じる保護者もいると思いますが、学校側でのフィルタリングは中学生レベルで考えています。また、登下校中にiPadを見ながら歩いたりすると危険なので、学校から離れたらYouTubeのアプリが消えるように設定しています。家庭ではMDM(モバイルデバイス管理)により、保護者の端末からコントロールが可能です。家ではあまりiPadに触ってほしくないと考えている場合は、時間によってiPadのアプリがすべて消えて時計だけになる設定もできます。
全てを学校で管理することも可能ですが、家庭での使用については子どもと話し合って家庭でルールを決めてほしいと考えています。それぞれの家庭で考えも違うと思いますし、保護者と子どもの関係の問題でもあるのです。思春期になれば、自然に今より会話は減ってしまうでしょう。今は、子どもとコミュニケーションを取れる大切な時期なのです。もし子どもが使い過ぎているなら、家族との大事な時間を削ってしまうことが問題だと思います。Wi-Fiも含めてどれくらいパケットを使っているか、子どもがどこにアクセスしているかなどもログで確認できるので、もし課題があると思ったときは、面談で話題にしてもらうように担任に伝えるなどの体制も整えています。
全てを学校で管理することも可能ですが、家庭での使用については子どもと話し合って家庭でルールを決めてほしいと考えています。それぞれの家庭で考えも違うと思いますし、保護者と子どもの関係の問題でもあるのです。思春期になれば、自然に今より会話は減ってしまうでしょう。今は、子どもとコミュニケーションを取れる大切な時期なのです。もし子どもが使い過ぎているなら、家族との大事な時間を削ってしまうことが問題だと思います。Wi-Fiも含めてどれくらいパケットを使っているか、子どもがどこにアクセスしているかなどもログで確認できるので、もし課題があると思ったときは、面談で話題にしてもらうように担任に伝えるなどの体制も整えています。

他国からも注目されるICT教育
私がADE(Apple Distinguished Educator)に選出されたのは、2019年です。iPadを導入してみて、もっと違う活用の仕方を知りたいと思ったのがきっかけでした。日本だけではなく、他国ではどのように活用しているかにも興味がありました。ICTに関するスキルだけでなく、教育に関する考え方、自分たちの学校だけで完結するのではなく、情報を発信して共有することで他の人たちにもよい影響を与えられるかなどで審査されます。ADEに選出されてからは、海外の事例を共有しやすくなりましたし、私もいろいろな情報を発信しています。台湾教育部(日本の文科省に相当)から30人ぐらいの方が本校を訪問した際には、授業やMDMの活用について英語で説明したこともあります。昨年は、アメリカから講演依頼があり、システムについて話しに現地へ行きました。
本校には私のほかに2人、ADEに選出された教員がいますが、それぞれ得意分野が違います。今後は、国語と映像、プログラミングと算数など、それぞれの得意分野と絡めてコラボなどもしていきたいです。
本校には私のほかに2人、ADEに選出された教員がいますが、それぞれ得意分野が違います。今後は、国語と映像、プログラミングと算数など、それぞれの得意分野と絡めてコラボなどもしていきたいです。

プログラミングの授業(3年生)を取材
プログラミングの授業はメディアルームを使って、3~4人のグループに分かれて座ります。この日の授業では、Springin'(スプリンギン)というプログラミングツールを使ってクレーンゲームのクレーンを作りました。土台となる部分は、前回の授業で作ってあります。榎本先生が作ったサンプルがサーバーに置かれているので、前回の授業でうまく作れなかった児童などはそれを使うこともできます。
榎本先生は、クレーンのアーム、十字キー、「開く」ボタンの説明をしましたが、「閉じる」ボタンについては詳しい説明をせず、子どもたちに考えさせました。子どもたちは、「開く」ボタンをヒントにして自分で考えたり、友達と相談したり、先生に質問しながらプログラミングしていきます。
出来上がったゲームを提出(アップロード)すると、他の子どもたちもそれをダウンロードして遊ぶことができます。ゲームの画像を綺麗に仕上げたい子、クレーンで取るものなどにストーリー性を持たせている子、とにかくゲームを完成させたい子など、それぞれの好みやペースで制作が進められ、個性豊かなゲームが完成しました。
榎本先生は、クレーンのアーム、十字キー、「開く」ボタンの説明をしましたが、「閉じる」ボタンについては詳しい説明をせず、子どもたちに考えさせました。子どもたちは、「開く」ボタンをヒントにして自分で考えたり、友達と相談したり、先生に質問しながらプログラミングしていきます。
出来上がったゲームを提出(アップロード)すると、他の子どもたちもそれをダウンロードして遊ぶことができます。ゲームの画像を綺麗に仕上げたい子、クレーンで取るものなどにストーリー性を持たせている子、とにかくゲームを完成させたい子など、それぞれの好みやペースで制作が進められ、個性豊かなゲームが完成しました。